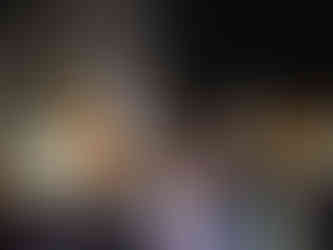ヒビコレ家族の小さな旅
- 2025年8月8日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年9月10日
夏祭りに行ってきました!

今回は日々家が夏前半に行った『夏祭り』リポートになります!
■ 宇都宮の夏祭りと言えば神輿に山車にパレードに、、、
みんなが集まる『宮まつり』
毎年8月最初の週末に開催される『ふるさと宮まつり』が、今年も8月の2日・3日に開催されました!


来場者数57万人との公表があった今回の宮まつり。「であいとふれあい」をテーマに、お神輿以外にも、ダンス、YOSAKOI、宮っ子パレードでは、友好都市の提携から1年を迎えた沖縄県うるま市の有志の団体が、地元の伝統芸能・エイサーを披露しました。



北関東最大となる54基の神輿の出場に加え、5年ごとのお披露目の山車がコロナでの中止を跨ぎ10年ぶりに登場した蓬莱町の彫刻屋台、各所で響く軽快なお囃子、そして威勢良く迫力満点の神輿渡御。
50回の節目を迎えた今年の宮まつりは、例年以上の熱気に包まれました!
祭り一番の盛り上がりは、最後に二荒山の神輿を神社にお返しする儀式「宮入り」。95段の参道石段を、威勢の良いバンバ商店街太鼓神輿の伴走で登ります。 ↓山門前にて



締めは、運営委員長による「十締め」で、感動の幕が閉じました。

【動画】太鼓神輿の宮入り
■ 夏を先駆けて開催される『天王祭』
毎年7月15日から20日にかけて行われる、宇都宮の夏始めの風物詩。
二荒山神社境内にある須賀神社(旧牛頭天王社)の例祭で、疫病を鎮める神である 素戔嗚尊 (スサノオノミコト) を祀っています。特に、子供神輿が市内を練り歩きオリオン通りでのぶっつけも交えた渡御はアーケード街に響き渡る見どころです。


【動画】天王祭 オリオン通りの様子
■ 日本一の移動式屋外歌舞伎『那須烏山 山あげ祭』
7月27日に烏山町の『山あげ祭』最終日に行ってきました!
山あげ祭りとは、那須烏山市烏山地区の八雲神社の祭礼で、460年以上の歴史を誇ります。八雲神社は牛頭天王(スサノヲ)を祀る祇園信仰の神社で、永禄3年(1560年)に那須資胤が疫病退散を祈願し、大桶村から神を勧請したのが起源とされています。
地元では「お天王さん」とも親しまれ、現在はユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」にも登録。山あげ祭では、山に神が宿るという信仰に基づき、竹と和紙で作られた「山」を舞台に、町を移動しながら歌舞伎が演じられる、日本でも独自性の高い伝統行事です。

今年はへび年とのことで、珍しい演目『蛇姫様(じゃひめさま)』が上演されました。
時は江戸時代、万治元年(1658年)。烏山の城では、城主・掘親良の娘・阿六姫にまつわる噂が広まり、人々が苦しめられていました。父へ真実を伝えるため、姫は家臣の腰元・楓に密書を託し、自らは命を絶ってしまいます。

楓は江戸を目指し、那珂川のほとりを一人で旅立ちます。澄んだ川面、そよ風に混じる祭り囃子……そこへ、姫の密書を狙う追っ手が現れます。
必死に逃れる楓。すると雷鳴とともに、白蛇が姿を現します。その白蛇は、阿六姫の想いと楓の忠義に心を動かされた神の化身でした。追っ手の剣をかわし、妖術で立ち回る白蛇。文箱をくわえた白蛇は、木々の間に消え、やがて姿を消していくのでした――。






若衆は歌舞伎の演台に常磐津の櫓、そして地元の特産「烏山和紙」で創作した「はりか山」を路上にあげ、奥行き約100メートルにも及ぶ大きな舞台装置を背景に、踊り子が常磐津の三味(しゃみ)にのり、美しい舞を披露し、一つの舞台が終われば次の場所に舞台を移動します。設営から演舞、撤収の間にもお囃子は延々と続けられます。この一連の作業を行うには約150人の若衆が必要とされ、その一糸乱れぬ団体行動による舞台装置の設置や解体、山があげられる場面は迫力満点です。 この祭りに、この場所には、仲間意識あふれる素晴らしい街、烏山です。